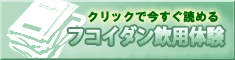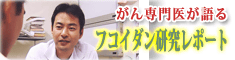肝臓がんについて
肝臓がんとは?
肝臓がんは肝臓にできるがんの総称です。
肝臓が発生元である原発性肝がんと、他臓器で発生したがんが肝臓に転移した転移性肝がんに分けられます。原発性肝がんはさらに組織型によって分類されます。
以下、良性腫瘍も含めて2000年のWHO histological classification of tumours of the liver and intrahepatic bile ducts の資料を元に分類し解説します。
- 上皮性腫瘍
- 良性
- 肝内胆管腺腫など。
- 悪性
- 肝細胞癌:肝臓の実質である肝細胞から発生するがん。日本では原発性肝癌の約90%を占めます。慢性肝炎や肝硬変を母地として発生します。
- 胆管細胞癌(肝内胆管癌):肝臓内の胆管から発生するがん。日本では原発性肝癌の5%程度。
- そのほか稀なものとして上記の混合型や肝芽腫などがあります。
- 非上皮性腫瘍
- 良性
- 血管腫など。
- 悪性
- 血管肉腫など。
- その他の腫瘍
- 孤在性線維性腫瘍など。
- 造血細胞性及びリンパ性腫瘍
- 二次性腫瘍(転移性肝癌)
- 他の臓器のがんが肝臓に転移したもの。頻度が高いのは、胃がん・大腸がん・膵がん・肺がん・乳がんなどです。
- 腫瘍に類似した、上皮の異常
- 過形成、異形成など。
- その他の腫瘍類似病変
原発性肝がんの大部分は肝細胞がんであることから、肝がんという言葉は狭義に肝細胞がんを指す場合があります。また欧米では胆管細胞がんは胆管がんの一部であるとする認識が一般的であり、肝癌≒肝細胞癌ですが、前述のとおりWHO分類などでは「肝臓および肝内胆管の腫瘍」とすることにより、実質的に一まとめにして扱っています。
肝臓がんの原因
はっきりとした原因はわかっていませんが、日本人に肝臓がんが増えている要因は肝炎ウイルスの感染者の増加が主因といえます。原発性肝臓がんでは、肝硬変患者の約半数にみられています。特にB型慢性肝炎、C型慢性肝炎から肝硬変に進展した症例や、肝炎ウイルスのうちB型肝炎ウイルスとC型肝炎ウイルス、特にC型肝炎ウイルスに感染した人が肝臓がんになりやすく、肝臓がんを発病した患者さんのうち、これらのウイルスに感染している人は実に90%近くに達しています。
アルコール性肝炎から肝硬変になった場合に肝臓がんが発症する率は低いとされていますが、日常的に酒量が多い人がウイルス性肝炎になり肝硬変になった場合には、かなり高い確率で肝臓がんが発生します。アルコール多飲者に肝臓がんの危険性が高く、老人の肝臓がんでは70%以上の症例でC型肝炎ウイルスに関連する抗体が発見されている。
したがって、肝炎ウイルスに感染しないことが肝臓がん予防にはとても大切であるといえます。
また、他の臓器のがんからの転移性肝臓がんでは、転移を起こしやすいがんとしては胃がん、膵臓がん、肺がん、大腸がん、胆嚢がん、子宮がんなどが挙げられます。
肝臓がんの症状
初期には自覚できる特有の症状はほとんどありません。症状がでるとしたら上腹部の右側に何となく膨脹感や不快感が生じるというものです。なぜなら、肝臓は非常に大きな臓器であり、健康な状態では十分な余力をもってからです。そのため、原発性の肝臓がんを発症しても、がんが成長するにつれて肝臓の体積、腹部の体積が大きくなるために、これが原因となる症状が最初に現れます。それが上腹部の右側に何となく膨脹感や不快感が生じるというものです。
肝炎や肝硬変から生じた肝臓がんの場合の初期の症状
- 食欲不振
- 倦怠感
- 腹部の満腹感
- 突然の腹痛
- 貧血
- 便秘や下痢
- 症状が重いときには、黄疸(血液中のビリルビンが増加して皮膚や粘膜が黄色くなる)、腹痛、腹水(腹腔内に体液がたまること。血液が混じることもある)、発熱、肝性昏睡などが起こることもあります。
肝硬変が進んだときの症状
- 男性でも乳房がふくらむ
- 手のひらが紅色になる(手掌紅班)
- 腹部の静脈が浮き上がる
- 下半身がむくむ
- 鎖骨の下あたりに赤い模様が生じる(クモ状血管腫)
肝臓がんそのものによって生じる症状には、強い脱力感、右の肩甲骨の痛み、みぞおちのしこり、腹部の腫れや痛み、体重の減少、黄疸などがあります。
肝臓がんの診断・検診・経過観察
検査項目
GPT, GOT, X線, AFP, CEA, 肝生検,腹部超音波など
- 血液生化学
- 腫瘍マーカー
- 肝細胞がんに特異的なものにAFP, AFP-L3分画、PIVKA-2が、胆管細胞がんや消化器がんの肝転移で濃度が上昇するものとしてCEA、CA19-9などがあります。
- AFP,AFP-L3分画 … 原発性肝癌の診断に有用
- PIVKA-II … 原発性肝癌の診断に有用であるが、ワーファリンの影響を受けるため、循環器疾患を合併する際には、留意が必要。
- 画像診断
- 超音波検査、CT、MRI、血管造影などが必要に応じて行われます。肝機能の検査:一般の血液生化学検査の他にICG負荷試験やアシアロシンチグラムなどが行われます。
- 超音波断層撮影,CT,MRI,血管造影
肝臓がんの治療
肝臓がんの治療法には外科治療(手術)と内科治療があります。
腫瘍の大きさや数、肝機能の状態により治療法が選択されますが、内科治療は格段の進歩をとげており、
- ラジオ波焼却療法
- マイクロ波凝固療法
- エタノール注入療法
- 肝動脈塞栓療法
などで、早期の肝臓がんでは十分コントロールが可能となっています。従って、肝臓がんの早期診断・早期治療が重要となっており、慢性の肝臓疾患では
- 血液検査(1ヶ月毎)
- エコー検査(病態に合わせ3〜6ヶ月毎)
- CT,MRI(6ヶ月毎)
が大切です。
ほかのがんと同じように、手術で取りきれれば根治する可能性がありますが、肝臓の機能が悪いと手術に耐えられません。つまり、肝臓の一部を取った後、残った肝臓が充分でないと手術後に肝不全に陥る危険があります。
肝臓がんの場合は肝硬変や慢性肝炎などを合併していてもともと肝機能の悪い患者さんが多いため、これは大きな問題です。さらに今後は肝硬変などの慢性の肝臓疾患から肝臓がんの発生を予防することが最も重要な課題となります。
肝臓がんの発生の予防では、
- グリチルリチン製剤(強力ネオミノファーゲンC)や小紫胡湯
- インターフェロン
などの有用性が報告されています。
手術に耐えられないと判断された場合は手術以外の治療法を選択します。最近は内科的あるいは放射線科的治療法の進歩によって、肝細胞がんの治療成績は向上しています。比較的小さながんを診断して治療すれば外科切除に匹敵する効果も認められています。
化学療法について
化学療法とは、一般的な言い方をすれば抗がん剤治療です。抗がん剤を投与してがん細胞を殺す治療法です。
しかし、抗がん剤治療には、吐き気・嘔吐・脱毛などのさまざまな副作用が生じます。
その副作用の苦しさは人さまざまですが、ほとんどの人が相当な苦しみを伴います。
その苦しみを軽減し、さらなる改善の効果を発揮しているのが現在注目の「フコイダン」なのです。
「フコイダン」は健康食品なのですが、代替医療として、世界中から注目されている成分なのです。
サブメニュー
サイトマップ
会の概要
がん治療のための「フコイダン療法・最新レポート」

メールアドレスを記入して登録してください。
5分以内にご記入のメールアドレスにがん治療のための「フコイダン療法・最新レポート」無料ダウンロードメールをお送りいたします。
※ファイルが見えない方は原本をお送りいたしますのでこちらまでお送り先をご連絡ください。
info@1mfk.com